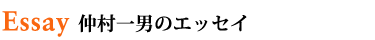
|
 |
 |
二十年ほど前、わたしはまだ大阪のある新聞社につとめていた。隣のビルにいろいろの店があり、そこのハキモノ屋にかわいい女店員がいた。からだが大きくて色が白く、笑うと口が両端からほころびるようにひらくのが特徴だった。
わたしはなんとか話すきっかけをつくるため、毎日ゲタを買うことにした。はじめのうちは両親のものや自分のを買っていたが、それもタネがつき、妹の赤いハナオの女物まで買うことになった。奥様のですかと彼女にいわれ、やっとぼくは独身だということができた。
うちではゲタがたまる一方だし、母もふしぎに思っている。先輩の奥さんが見かねて先方へもらいにいってくれた。ところが、ことわられましたよといわれ、わたしはチクショウと思って、あくる日すごい顔で彼女をにらみつけた。色の白いその顔がますますすきとおるように白くなった。しばらくして彼女の姿は見えなくなった。
終戦になり海軍から帰ったわたしは、ある日、彼女といっしょに働いていた店員に会った。そこで、あの子はかわいそうに胸が悪く、わたしがもらいにいったとき、お医者様に相談したが、結婚は無理だといわれ、それから半年ほどしてなくなったことを知った。
それでも春だったか小雨の降る夕方、いっしょに御堂筋の並木道を歩いたことがある。淀屋橋まできて、地下鉄の入り口で、彼女はからだをかがめ、雨にぬれたタビをぬいだ。そのとき、耳のうしろの美しいのと、タビをぬいだ足の、目にしみるような白さをわたしは見た。
※「思い出のひと」欄(新聞掲載分・昭和39年1月10日、紙名不明) |
[エッセイトップ]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] |


